<取材・執筆>北原 杏菜 <取材先>「生きる」大川小で起こったこと 上映会 実行委員会 藤原 貞子さん

東日本大震災発生時、宮城県石巻市立大川小学校で、津波に巻き込まれた74人の児童(うち4人は行方不明)と10人の教員が命を落とした。地震発生後、大津波警報が発令されるなか50分校庭にとどまり、高い裏山に避難誘導しなかったなどの問題が指摘されている。
この出来事を取り上げたドキュメンタリー映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』が、2024年9月8日神奈川県逗子市の逗子文化プラザにて上映された。映画に登場していた遺族と弁護士、そして監督が登壇するトークイベントもあわせて行われた。
今回は、本イベントの様子と、自主上映会の発起人である藤原貞子さん(80)のお話を紹介する。
映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』
本来子どもたちを守るべき場所である“小学校“で起きたこの惨事。震災発生後、石巻市教育委員会が実施した保護者説明会や、第三者組織である大川小学校事故検証委員会(防災や教育に関する専門家によって構成)による検証報告で、事故発生時の説明が行われた。
しかし、映画によるとそれらの場では決して遺族たちの声が第一に聞き入れられることはなく、遺族が本来知りたかった、子どもたちの死の経緯や事故発生に至った理由が明らかにされることはなかったそうだ。こうした状況のまま、保護者説明会の打ち切りや検証委員会の検証終了が決まった。一方的ともいえる決定を飲み込まざるを得ない不当な扱いを受けた遺族たちは、真相究明を願い国家賠償請求訴訟を起こした。
『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』は、地震発生後から控訴審後までの期間、遺族たちと、弁護人となった吉岡弁護士と齋藤弁護士を映した作品である。
500人が見入った、10年の記録
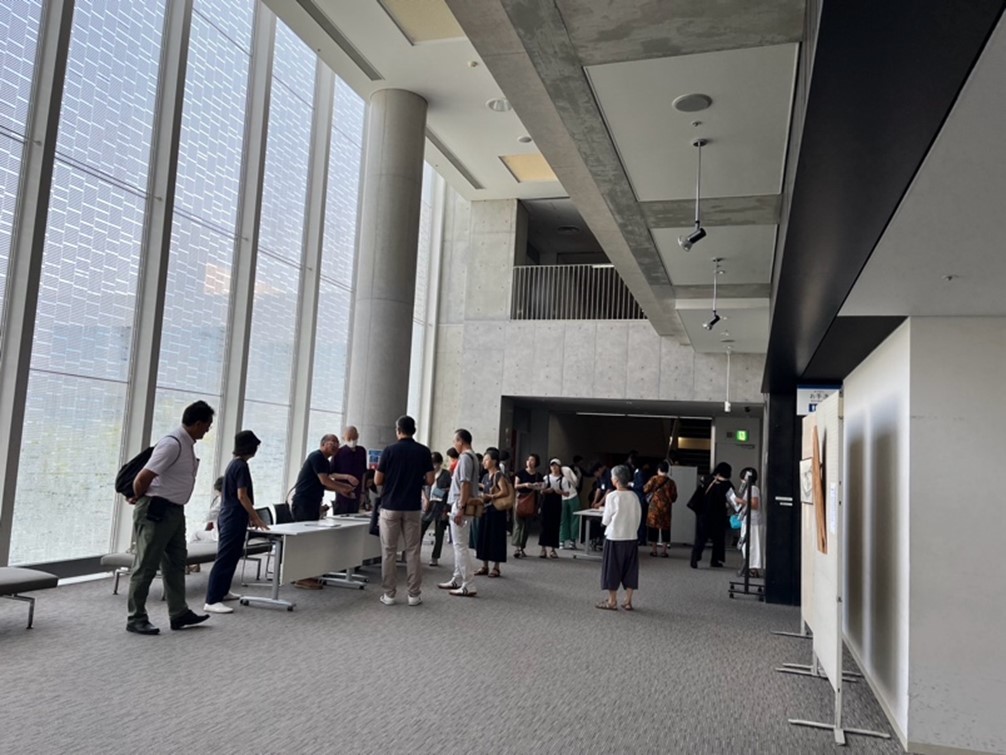
上映会・トークイベントには、満員の約500人の観客が集まった。観客の年代は幅広く、中高生くらいの若者もいた。
上映の前に上映会発起人の藤原さんからスピーチがあった。
「人は穏やかな日常を送るために、辛い記憶は消したいと思う。でも一方で忘れてはいけないという気持ちもある。辛い映画と分かっているのに、時間をかけ、お金を払ってここまで来るのは勇気ある行為で、そういう人がこんなにたくさんいるって凄いことだと思う。また遺族の方々は、私たちの何十倍、何百倍も辛い記憶を、石巻から逗子までやって来て大勢の前で話される。何百倍、何千倍もの勇気をお持ちです。この会場は勇気ある人びとで一杯になっています」
この言葉で観客席は引き締まった。映画は、震災直後の大川小学校と石巻市教育委員会とのやりとり、検証委員会の様子、国家賠償請求訴訟と進む合間に、遺族の方々や弁護士のインタビューが入る。
観客は真剣に見入り、緊張感のある空気が漂っていた。
トークイベント:映画を通じて語られた記憶と再生

映画上映と休憩の後、舞台上に本映画を制作した寺田和弘監督、遺族の今野浩行さん・ひとみさん夫妻、紫桃(しとう)隆洋さん、齋藤雅弘弁護士が登壇された。
トークイベントは寺田監督の進行のもと進められた。前半は登壇者のトーク、後半は観客からの質疑応答が行われた。
5人の話の中では、映画本編では語られなかった事実にも触れられた。
例えば、控訴審にあたって原告団から誰1人抜けなかったのだが、控訴するにあたり手数料が更に必要になったため、経済的にも原告団のメンバー同士で支え合ったと今野浩行さんは説明した。遺族たちが強い意志を持って裁判を起こしたことが伝わり、単なる美談では片づけられないと感じた。
今野ひとみさんは、当時小学6年生だった息子の大輔さんのエピソードを紹介する一方で、生き残った児童に対する心のケアが不十分だったことを説明し、遺された人の「こころの復興」も道半ばであると語った。
石巻市で消防団に所属していた紫桃さんは、当時の大川小学校の津波状況やご自身の経験を丁寧に説明。消防団の経験からも、いかに自分ごととして地震に備えることが大切かを示した。現在行っている語り部活動に関しては、娘を思い出し辛くないというと嘘になるが、同時にそれが供養でもあるとの思いを語った。今野浩行さんとともに、防災の必要性を訴え、誰にも決して同じ辛さを味わって欲しくないという思いを示した。
齋藤弁護士は、津波で全て無くなった状況から証拠を探すことや、原告団以外の保護者から証言を集めることがどれほど難しかったかを語った。遺族の方々と協力しながら進めるにつれ思いの強さ、素晴らしさを知り、なんとかして応えようという気持ちが芽生えたと力強く語った。
観客は、映画に登場されていた遺族の方々を前にして、その強い思いを受け止めたいという一心で、より一層の緊張感に包まれていた。
教師の経験と映画が結ぶ絆 藤原さんへのインタビュー

今回このイベントに際し、発起人の藤原貞子さんのお話を伺う機会をいただいた。
長年教師として働いていた藤原さんは、今年4月に神奈川県横須賀市で行われた「生きる」上映会に観客として参加していた。その際、本映画を観て涙が止まらなくなった。背景には自身の教師としての経験が強く影響していたという。藤原さんは教師時代、不慮の水難事故で教え子を亡くした経験があり、その記憶がさらにこの映画への思いを加速させた。
辛い出来事の記憶は多くの人が目を背けてしまうが、「なかったことにする」行動が遺族をより苦しめてしまうと強く感じた藤原さんは、より多くの人、特に教師をはじめとした学校関係者に本映画を見てもらいたいという使命感を持った。最初は手探りで情報を集め、その結果、自主上映を行うことが最善の方法であることを知った。
インタビュー時、「自主上映会の実行委員会はどのようなメンバーで構成されているのですか?」と尋ねた私に対し、藤原さんは「実行委員会という大それた名前を出しているけど、私が周囲の人に呼びかけたら、協力が広がっていったのが実際のところなの」とお茶目に笑ったのが印象的だった。
その言葉の通り本イベントは発起人の藤原さんが中心となり、藤原さんが通う座禅会や絵画教室、テニスクラブの友人や先生、高校の同窓生や教え子、4月に横須賀で行われた上映会を主催した「16ミリ試写室」のメンバーに至るまで、多くの人の参加・協力があってこそのものだったという。藤原さんは、その一人一人に直接、映画についての思いを時には涙ながらに伝えていった。「素朴な原動力が響いて、皆さんが動いてくださったのね」と藤原さんは当時を振り返った。
協力メンバーの中には、ICTが得意で広報担当を務める人や準備を手伝えないからと活動資金をくれた友人、自分の飲食店でチケットを多く売り捌いてくれた教え子一家など、様々な角度から活動を進めてくれた人たちがいたという。藤原さんも、葉山町や逗子市の校長会に出席し本イベントについてのスピーチをしたり、地域紙「タウンニュース」へ記事掲載を直談判し掲載してもらったりなど、精力的に活動を進めていった。協力メンバーたちの姿が藤原さんの活力・原動力となった。「会う人会う人を巻き込んでいったけれど、これが“究極の市民活動”なのかもしれないわね」と藤原さんは語った。
開催前にお話を伺った時に、より多くの人に見ていただくためにもチケットを買っていただくことが課題と語っていた藤原さん。当日、会場の入り口にあるポスターには「満員御礼」のステッカーが貼ってあった。イベント実施後、チケット完売について聞くと、「生の人が直接語りかけることが功を奏して、これだけの人が集まってくれたのだと思う」と藤原さんは振り返った。
上映会にあたって、観客がどのような思いを持つか、映画や遺族たちの声がどのように伝わるかを考えていた藤原さんだが、反応は想像以上だったそうだ。当日回収したアンケートの回収率も高く、中には書ききれないからとメールをくれた人もいたそうだ。
死を無駄にしないため多くの人に知って欲しい
当日の観客たちの声から藤原さんが強く感じたことは、「世の中を良くするために役に立ちたいという心を大勢の人が持っている」ということだった。今回のイベント実施のきっかけは、藤原さん自身が横須賀にて本映画に出合ったことだった。それが藤原さんの教師経験というフックに引っかかり、この映画を通じて大川小学校で起こった出来事をより多くの人に知って欲しいという強い思いを生んだ。
遺族は今なおその現実と闘っており、それが終わることはなく、「悲しい出来事」「対応が悪かった」などで簡単に納まるものではない。そうした中でも子どもたちの死を無駄にしないための手段が、映像に事実を残すことだった。映画を観てもらうことで子どもたちは、もう一度生きることができる。受け入れきれない現実を突き抜けてまでも「生きる」人々の姿を追った、前に進むための作品であると藤原さんは強く語った。
最後に、今後また上映会をする予定はありますかと伺ったところ、「今は実施する予定はないし、“一発勝負”だったからこその良さもあったように感じている」と藤原さんは答えたが、その直後に「また上映会を実施してという声もあるけれどね」と言い、笑った。同じかたちではないかもしれないが、心強い“チーム”である周囲の人々とそれを巻き込む藤原さんの行動力と強い思いが、多くの人々の心を動かす機会は今後もきっとあるだろう。
